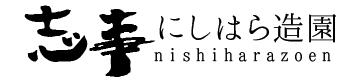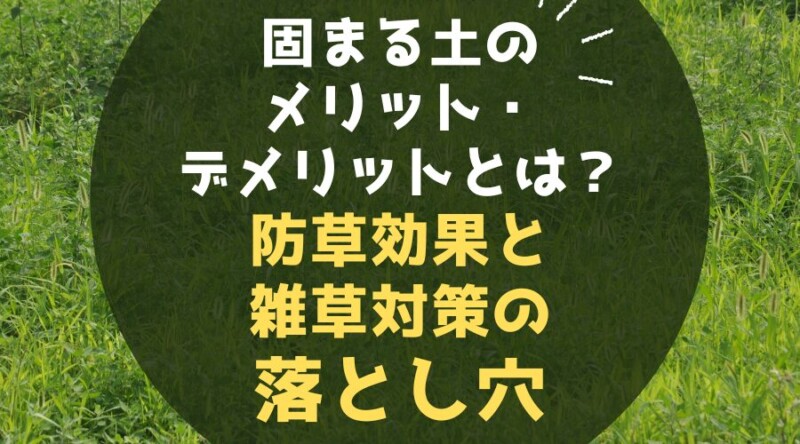固まる土を使った雑草対策は、見た目がすっきりして手入れもラクになりそうな印象から、ここ数年で急速に人気が高まっています。
しかし、その一方で「ひび割れがひどい」「雨のあとに水たまりができる」「苔が生えてきて見た目が汚くなった」といった声も増えてきました。
あなたも、施工を考えていた矢先に“固まる土 デメリット”で検索し、不安になったのではないでしょうか?
実際に私が現場で相談を受ける多くの方が、youtubeやSNSなどでは“良くない事”ばかりを聞かされ、「使っても大丈夫かな?」「うちの庭に合ってるのかな?」と迷いながら連絡してこられます。
問題は、固まる土には“向いている場所”と“向いていない環境”がハッキリ存在することです。これを無視して施工すると、高確率で後悔します。
でも安心してください。本記事では、固まる土の具体的なデメリットとその発生原因、避けるための製品選びや施工ポイント、他の雑草対策との比較まで、すべて網羅的に解説しています。「正しい知識」を持って選べば、後悔のない防草対策ができるはずです。
この記事を読むと以下のことがわかります:
- 固まる土で起こりがちな代表的なデメリットとその原因
- デメリットを防ぐための製品選び・施工前の準備ポイント
- 防草シート・砂利・コンクリートとの比較と使い分け
- 長期的な劣化や撤去コストを踏まえた判断基準
- DIY施工でよくある失敗とその回避策

西原造園の代表で職人歴20年以上の現役の造園・庭・外構の職人。施工実績500件以上。施主様の生活背景や状況を理解し戸建ての庭のリフォームをメインに外構・造園・エクステリアプランを作成したり、特にお庭の問題を解決するのが得意。全国紙ガーデン&エクステリアの掲載歴があり、父は一級造園技能士、母は奈良新聞にも掲載された一級造園施工管理技士。仕える事と書いた仕事ではなく、志す事と書いた「志事」をするがモットー。
知らないと損する固まる土のデメリットとリスク
固まる土は一見すると「便利で手軽な防草素材」ですが、実際の施工現場では多くのトラブル報告があります。この章では、表面的な紹介では語られにくい固まる土のリスクやデメリットについて、原因・背景・現場事例を交えて詳しく掘り下げていきます。
固まる土のひび割れ・剥がれが起こる原因と対策

「数ヶ月でひび割れが起きた」「表面が剥がれてボロボロになった」──これは、私がこれまで最も多く相談を受けた固まる土のトラブルです。特に多いのはセメント系の固まる土で、冬場の施工や水勾配不足の状態です。
原因のほとんどは、下地の締固め不足です。
例えば、転圧が甘いと施工後に地盤が沈下し、表面だけが割れて浮いてしまいます。また、セメント系は乾燥によって収縮しやすいため、気温差が激しい季節に施工すると、すぐにクラックが入ることも。
対策としては、使用場所に応じた製品選び(例:天然素材系)、および下地の施工精度の確保が必要です。特に地面の締固め・水勾配(最低でも1〜2%)の確保は、DIYでも絶対に省いてはいけないポイントです。
また広い範囲を一気に施工するとクラックが入りやすいので、10㎡~20㎡ごとに伸縮目地やレンガなどで区切りをつけると比較的クラックは入りにくいです。また、必要に応じてメッシュ筋などを敷くとよいです。(特にあるくところなど)
現場では、目立たない場所にはコスト優先でセメント系を使い、人の通る場所は割れにくい製品を選ぶと、補修や再施工の手間が大きく変わります。
とはいえ、固まる土は基本的にヘアクラック程度は必ずと言っていいほど発生します。これは施工ミスではなく、そもそもそういう商品なので、ヘアクラックの発生を許容できない場合は他の雑草対策を取ったほうがよいです。
水たまり・ぬかるみが起きる原因と対策

「水が引かない」「ぬかるみができて歩けない」──こうした声も非常に多いです。水はけが悪いと、見た目も悪くなり、苔やカビの発生にもつながります。
固まる土自体にも一定の透水性はありますが、降雨量が多い場合や連日の雨では処理能力を超えてしまい、オーバーフローして地表に水がたまるケースもあります。つまり、“透水性があるから大丈夫”という前提だけでは不十分で、排水の設計まで含めて考える必要があるということです。
原因の大半は、以下の通りです:
- 勾配不足や逆勾配による水たまり
- 透水性の低い製品(特にセメント系)を平らに施工
- 地盤そのものの排水性が悪い(土質が粘土質など)
- 排水先がない(排水口や側溝が設計されていない
実際、私の現場でも「見た目を重視して平らに仕上げてくれ」と依頼されたことがあります。しかし、フラットに仕上げるほど水勾配が取れず、雨のたびに水たまりが発生するという本末転倒な事態になりかねません。
対策として重要なのは、必ず水勾配を取ること(1〜2%)と、そして排水先を明確に設けることです。排水口や側溝、浸透マスなどに水を逃がせる設計ができていないと、せっかく勾配を確保しても行き場を失った水がたまり、苔やカビ、劣化の原因になります。
DIYでは見落とされがちですが、水が逃げ場を失うと、何日も水が引かないという原因にもなります。
固まる土で苔やカビが発生する原因とその対策方法

「見た目が汚い」「黒色に変色してきた」──これは、特に北側や日陰・湿気が多い場所に多く見られる現象です。固まる土はあくまで“土を固めたもの”なので、表面が湿る状態が続くと苔やカビが発生するのは自然なことです。
また、現場での経験として、汚れたブロック塀や古いコンクリートのすぐ近くに固まる土を施工した際、そこから雨で流れ落ちた汚れや藻が染み出し、表面に黒ずみや変色を引き起こすケースもあります。水はけや通風だけでなく、“周辺構造物の汚れや排水経路”も影響するため、施工前に周囲の状況を確認しておくことが重要です。
他にも、私が経験した現場では、通風が悪く、隣家との距離が近い場所に施工したところ、半年で苔が一面に広がったケースもありました。
原因としては:
- 日照不足(特に北向きや建物の陰になりやすい場所)
- 排水性が悪く、地表に水分が長く滞留する構造
- 汚れたブロック塀や古いコンクリートから雨水により汚れが流れ込む
- 施工後の表面清掃が行き届かず、種子・埃・有機物が堆積している
対策としては、施工前に「その場所が苔の発生リスクが高い環境か」を見極めることが第一です。とくに周囲の構造物にカビや汚れが既にできてる場合は高確率で固まる土もよごれてしまうので、その場合は、防草シート+砂利などの別素材も検討するのが現実的です。
また、施工後も定期的なブラッシングや、日陰部分の水掃き・清掃を行うことで、苔の繁殖を抑えることができます。
固まる土の耐久性・寿命に関する誤解と真実

「一度施工すれば10年以上持つと思ってた」という声も少なくありませんが、これは誤解です。固まる土の寿命は、製品・施工方法・使用状況によって3〜10年と大きく幅があります。
耐久性に影響する主な要因は以下の通り:
- 製品の種類(セメント系・天然系)
- 人や車がどの程度通行するか
- 施工の精度と下地処理の質
- 地域の気候(寒冷地は特に割れやすい)
現場感覚としては、よく踏まれる場所は3年~5年程度で劣化が始まることが多いです。特に表層が粉を吹いたり、表面の粒が剥がれてくることがあります。
長持ちさせるには、「施工精度」と「部分補修によるメンテナンス」の両立がカギです。耐用年数を鵜呑みにせず、必要に応じて3~5年ごと(長く持って10年)のメンテナンス前提で選定・設計することをおすすめします。
DIY施工で起こる固まる土の失敗例と防ぎ方

DIY施工での失敗も多く、私が過去に補修を依頼された例では、9割以上が「下地処理不足」「勾配設計ミス」「施工の際の水加減」でした。
具体的な失敗例としては:
- 地面を均さずにそのまま施工 → 凹凸ができて水たまりの原因に
- 転圧をしていない → 地盤が沈み、表面にひび割れや剥がれが発生
- 水を与えすぎてしまう → 表面が砂状化し、養生しても固まらずボロボロに崩れる
- 雑に水をかけた →かかっていない部分が上手く固まらず砂状化する
- 勾配を取らず平らに施工 → 雨水が流れず、ぬかるみや苔の発生源に
DIYで成功するためには、プロと同じ手順と精度を意識する必要があります。特に、転圧をすること、水分量の管理、道具の準備は欠かせません。
「材料を買ってきて、家族で休日に簡単に施工」という感覚で臨むと、結局数ヶ月後に業者に頼んでやり直し…という二重コストが発生します。DIYで挑戦する場合は、事前にしっかり学習し、できれば小面積から試して慣れることが重要です。
固まる土の撤去は難しい?将来的な費用と注意点

「将来植物を植えたいから一部だけ戻せるようにしたい」といった相談も多いのですが、固まる土の撤去は想像以上に大変です。特にセメント系や、厚く施工されたものは、電動ハンマーなどを使って壊す必要があり、撤去費用も高額になります。
目安としては、1㎡あたり4,000〜6,000円程度の撤去費用がかかることもあります。しかも、撤去後に再度整地・再施工する必要があるため、トータルでは施工費以上のコストになるケースも。
将来的に用途変更の可能性がある場所には、簡易施工(表面のみ)や、砂利+防草シートの併用を選ぶのが合理的です。
また、「撤去が必要になるかもしれない場所は、初めから施工しない」という判断も重要。現場ではこの“撤去前提のゾーニング”が失敗を避ける大きな鍵になります。(あくまでも撤去が必要になりそうな場合ですが)
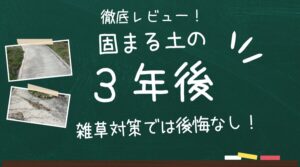
固まる土のデメリットと失敗を避ける対策と選び方
固まる土は一見便利な建材ですが、選び方や施工方法を間違えるとトラブルが起こりやすい素材でもあります。この章では、デメリットを最小限に抑えるために「製品選び」と「施工前の準備」に着目し、失敗しないためのポイントを具体的に解説します。
固まる土のデメリットを軽減する製品選びと注意点

「どの製品も固まる土は同じだと思っていた」という声をよく耳にしますが、実際はメーカーや種類によって耐久性・透水性・仕上がりの見た目が大きく異なります。現場でよく使われるのは、セメント系、天然系の2種類ですが、それぞれ性質が違います。
セメント系は固まりやすくコストも安い反面、ひび割れしやすく水はけも悪い傾向があります。天然系は環境負荷が低くナチュラルな仕上がりになるものの、価格がやや高めです。
現場での判断基準としては、「その庭の環境(排水性・日当たり・人の動線)に合っているか」を最優先です。たとえば、日陰で湿気の多い庭に水はけの悪い製品を使えば、あっという間にカビや苔の温床になります。また、犬や子どもが頻繁に走り回る場所には、表面が硬すぎず割れにくい強度の高い製品が向いています。
製品の選定ミスはそのまま“デメリットを引き起こす元”になります。事前に複数製品の透水性・耐久性・施工実績を確認し、業者に実際の使用実績を聞いてみることが肝心です。
固まる土の施工前にやるべき準備と下地処理の重要性

「製品選びは慎重にしたのに、数ヶ月でボロボロになった」という相談もあります。原因の多くは施工前の下地処理の不備です。これはプロでも手を抜きがちなポイントで、DIYでは特に要注意です。
実際の現場では、施工前に「地面の締固め」「排水計画」などを入念に行います。特に重要なのが地盤の締固めと水勾配の確保。これが甘いと、施工後に土が沈んでひび割れが起きたり、水たまりが発生して苔・カビの原因になります。
施工前にやるべき基本的な準備は以下の通りです:
- 地面の草や石をしっかり取り除く
- 水勾配を考えながら「土を鋤き取る」
- 水勾配を考えながら「整地」する
- 転圧機またはプレートでしっかり締め固める
- 固まる土自体の水勾配(1〜2%程度)を確保する
これらのステップを省略せず、“水が溜まらない・沈まない・雑草が生えない”下地をつくることが最重要です。
現場経験上、「地盤が緩いのに施工してしまった」「水勾配が逆勾配になっていた」などの初歩的なミスが、後から大きなデメリットとして跳ね返ってくるケースが非常に多いです。
DIYで施工する方も、最低限この準備だけは丁寧に行うようにしてください。プロに依頼する場合も、下地処理の工程を具体的に確認することをおすすめします。
固まる土のデメリットと他の雑草対策との比較
固まる土のデメリットを正しく理解するには、それ単体で評価するだけでなく、他の防草対策と比較しながら検討することが重要です。この章では、防草シート・砂利・コンクリートという代表的な選択肢と固まる土を比較し、それぞれのメリット・デメリット、向き不向きについて整理します。
固まる土と防草シートの違いとデメリット比較

「防草シートと迷っている」という声は非常に多く、実際、両者は施工方法も用途も似ています。しかし、大きな違いは“表面の仕上がり”と“耐久性”です。
防草シートは下地に敷くだけで雑草を防げる手軽さがあり、コストも安く施工も簡単というメリットがあります。一方で、見た目が安っぽくなる・強風でめくれる・耐用年数が短い(劣化が早い)などのデメリットも。特にホームセンター品など耐久性の低いシートは、数年でボロボロになります。
対して固まる土は、仕上がりが自然で見た目がすっきりし、上を歩ける・自転車が通れるなど実用性も高いのが特徴です。
また、防草性能そのものを比較すると、適切に施工された固まる土の方が防草効果は高くなります。防草シートは、壁際やシート同士のつなぎ目、ピン穴などから雑草が生えてくるケースが多く、経年劣化による隙間や破れも防ぎにくいためです。一方、固まる土は面でしっかり固まり、隙間ができなければ草が生える余地がほとんどありません。
判断のポイントは、「見た目と歩きやすさを取るか」「防草効果とコスパを取るか」。例えば、日常的に使う動線なら固まる土、花壇の周囲や人が通らない場所には防草シート+砂利の方が合理的です。
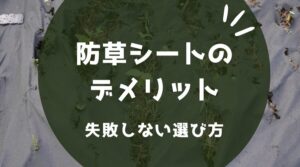
固まる土と砂利を比較!デメリットの差と使い分け

「砂利と固まる土、どっちがいい?」という質問もよく受けます。結論から言えば、使用目的と庭の環境次第です。
砂利は非常に安価で、見た目のバリエーションも豊富。施工も簡単で、DIYでも十分対応できます。雑草対策としては、厚く敷けばそれなりに効果ありですが、時間が経つと踏み固められて隙間ができ、雑草が生えてきやすいのが難点です。また、掃除がしにくい・子どもや高齢者が転倒しやすいといった声も多く聞かれます。
一方、固まる土は一度施工すれば、掃き掃除もしやすく、見た目も整うため、メンテナンス性は非常に優れています。ただし、雨が多い地域や傾斜がある場所では水はけが悪くなるリスクがあり、施工ミスがあるとひび割れ・ぬかるみが発生しやすいです。
実際の現場では、**「建物の周囲や歩く場所は固まる土」「外周部や人が通らないエリアは砂利」**というように、用途で使い分けるケースが最も合理的です。
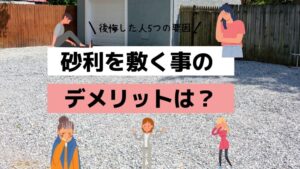
固まる土とコンクリートを比較した場合の注意点
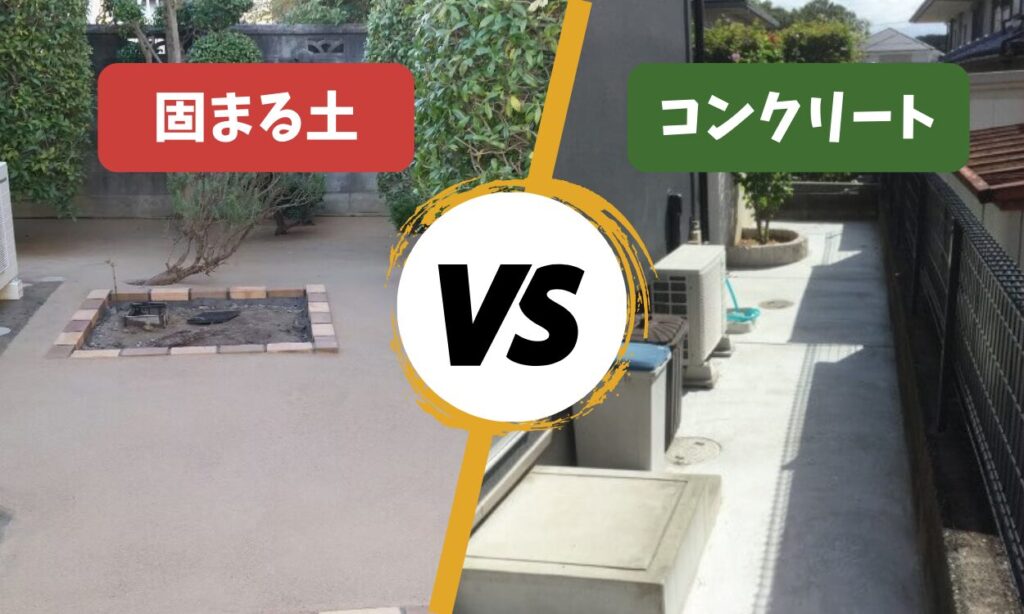
「長く使うならコンクリートの方がいいのでは?」という相談もよくあります。確かに、耐久性だけを見ればコンクリートの方が圧倒的に上です。10年、20年単位で持たせたい場合、コンクリートは非常に安定した素材です。
しかし、固まる土とコンクリートにはいくつか決定的な違いがあります。
まず、施工コスト。コンクリートは材料費・人件費ともに高く、1㎡あたり1万3000円以上かかることも珍しくありません。一方、固まる土は材料費・施工費含めて**1㎡あたり6,000〜10,000円程度**で収まるケースが多く、コスト差はおおよそ1.3〜2倍程度になります。
また、コンクリートは完全に硬化してしまうため、撤去やリフォームが非常に大変で高額です。それに比べて固まる土は、表面が多少劣化しても表層だけを補修できるため、部分的なメンテナンスがしやすいという利点があります。
この場合用途の違いで選ぶのが正解です。例えば、駐車場や車の通る場所や、バイクや自転車などの駐輪場はコンクリート推奨。それ以外の通路・庭まわりは固まる土で十分なケースが多いです。
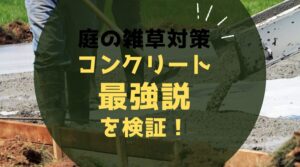
固まる土が適しているケースと不向きなケースの判断基準
固まる土が“どんな庭にも使える”わけではありません。むしろ、条件に合わない場所に使うと失敗率が高い建材です。
適しているケースは、以下のような条件がそろっている場合です:
- 歩道や犬走りなど、軽歩行程度の荷重がかかる場所
- 水はけの良い土地、または勾配がしっかり確保できる敷地
- 人目に付く場所で、見た目の仕上がりを重視したい場合
- 自分で掃除・メンテナンスがしやすい庭を目指したい場合
- 駐車場のスリット(目地)や石畳の目地など
逆に不向きなケースは以下の通りです:
- 湿気が多い・日陰で苔が生えやすい土地
- 車の出入りが多い・重たい荷重がかかる場所
- 雨が多く水たまりができやすい環境(排水計画が困難な敷地)
- 将来的に植物を植える・撤去する可能性があるエリア
私の経験上、「向いていない土地条件を見極めずに施工したケース」でのトラブルが非常に多く、施工後1年以内に補修・撤去を依頼されるケースもあります。迷った場合は、必ず施工業者に「この土地に向いているのか?」を相談し、代替案(砂利やシートなど)も視野に入れて検討するのがベストです。
固まる土(砂)はあなたに合っている?防草効果と雑草対策を再考しよう!
固まる土は雑草対策として多くの家庭で選ばれていますが、すべての環境や目的に最適とは限りません。この章では、固まる土の仕組みや防草効果、見た目の特徴を整理しながら、「あなたの庭に本当に向いているかどうか」を見極める視点を解説します。
そもそも固まる土とは?基本的な仕組みと種類

固まる土は、水を加えることで硬化し、雑草の発生を防ぐ土系舗装材の一種です。主にセメントや、マグネシウムなどの天然素材などを混合した製品が多く、乾燥や化学反応によって硬く固まり、雑草の根を張らせない構造を作ります。
セメント系は最も多く流通しているタイプで、固まりやすく、短時間で施工が終わる利便性が魅力です。ただし耐久性が低く、ひび割れや剥がれが起きやすいのが難点。あとは見た目がコンクリートに近くなるため、おしゃれ度は下がります。特に寒冷地や雨の多い地域では、収縮によるクラックが目立ちやすくなります。
天然系はマグネシウムなどを使った環境負荷の少ない素材で、自然な色合いで自然な風景に溶け込みながら雑草を抑制する事ができます。要するに「おしゃれ」です。
私の施工経験では、基本的には天然系を推奨しています。お庭の景観が崩れないからです。とはいえ、どれが優れているというより、「あなたのお庭の使い方や、庭の条件に合ったタイプを選ぶ」ことが重要です。

固まる土の防草効果と機能的メリット:どこまで雑草対策できるのか?

固まる土の最大の魅力は、表面がしっかり固まり、雑草が根を張れない状態を維持できるという点です。適切に施工すれば、3〜5年程度はほぼ雑草が生えない状態を保てるため、メンテナンスの手間が大幅に軽減されます。
見た目も自然でおしゃれに仕上がるため、「砂利だと野暮ったい」「コンクリートだと味気ない」という方にも人気があります。さらに、透水性の高いタイプを選べば、雨の日にも水たまりができにくく、泥跳ねやぬかるみを防げるのもメリットです。
ただし、施工不良(隙間がある・薄く塗ったなど)があると、そこから雑草が生えてくることがあります。また、土が表面に流れ込んでくると、土の上から雑草が発芽して、雑草だらけになってしまったという事例も多くあります。
対策としては、施工時に厚みをしっかり確保し、隙間のない均一な仕上がりにすること。さらに、施工後も定期的な掃き掃除で表面の土やごみを取り除くと、雑草が定着しにくくなります。
また、土が流れてこないよう土留めをしておくことも重要です。
現場では、「手間をかけたくない」「掃除を頻繁にしない」ご家庭には、固まる土と防草シートの併用や、部分的に砂利を重ねる方法も提案しています。防草性の高さだけでなく、ライフスタイルに合った維持のしやすさまで含めて選ぶことが、満足度の高い雑草対策につながります。
おしゃれに仕上げたい人こそ知っておきたい、固まる土の“見た目の落とし穴”

「無機質な防草シートやコンクリートは避けたい」──そんな思いから固まる土を選ぶ方は少なくありません。自然な風合いを保ちながら防草効果も期待できることから、ナチュラルガーデンや洋風の住宅デザインとも相性が良く、“おしゃれな庭づくり”を目指す人たちに注目されています。
実際、固まる土は施工後も“土の見た目”を残せるため、植栽やウッドフェンス、枕木などとも調和しやすく、景観を壊しません。表面がしっかりと固まり、雑草の根が張りにくいため、機能性とデザイン性を両立できる素材として非常に魅力的です。私が携わった案件でも、デザイン住宅やモデルハウスでの採用率は年々高まっています。
しかし、見た目の仕上がりにこだわる方ほど注意が必要な“落とし穴”がいくつか存在します。

とくに多いのが、「割れてチープに見える」「苔が広がって黒ずむ」「施工直後は良かったのに、数ヶ月で汚れが目立つようになった」という後悔の声です。
原因の多くは、素材選定・施工方法・施工場所のミスマッチにあります。たとえばセメント系の固まる土は、価格も手頃で施工も簡単な反面、色味が単調で、仕上がりがコンクリートに近くなるため、ナチュラルな印象とはやや離れます。加えて、ひび割れや割れ欠け・砂状化が起きやすく、時間が経つと見た目が劣化しやすいという特性も。
また、日陰や湿気の多い場所では、表面に苔やカビが発生しやすく、黒ずんで不潔な印象になることもあります。 ブロック塀やコンクリート床など、汚れのある場所と接していると、そこからの水垂れが原因で変色することも。
これらは“防草材”としての機能には直結しないものの、「見た目重視で選んだのに、残念な仕上がりになった」というケースを頻繁に目にします。

こうしたトラブルを避けるには、使用環境に合った製品選びと、丁寧な施工計画が不可欠です。 天然系や砂系の固まる土は、色味や質感に優れ、経年変化も自然に見えるため、美観重視の庭に向いています。
また、水が溜まりにくいように水勾配を確保し、表面が湿った状態を長時間放置しないよう通風や掃き掃除にも配慮しましょう。
見た目を優先して固まる土を選ぶこと自体は間違いではありません。ただし、素材の性質と施工条件を無視すれば、“理想の景観”が“劣化した地面”に変わってしまうリスクがある──ということだけは、知っておいて損はありません。
固まる土のデメリットに関するよくある質問と解説
固まる土は便利で見た目も良い建材ですが、施工後に「思っていたのと違った」「こうなるとは知らなかった」と後悔される方も少なくありません。この章では、実際の現場でよく寄せられる疑問に対して、プロの視点から具体的にお答えします。
固まる土の上に砂利を敷くとどうなる?
「見た目を変えたい」「もう少し柔らかい印象にしたい」といった理由で、固まる土の上に砂利を重ねたいというご相談をよく受けます。結論から言えば、敷くことは可能ですが、用途によっては注意が必要です。
まず、砂利を敷くことで見た目がやわらぎ、ナチュラル感が増すため、デザイン的には効果があります。歩くときの音も抑えられるので、防犯対策にもなります。ただし、注意したいのは以下の2点です。
- 砂利の種類と粒サイズによっては滑りやすくなる
- 掃除やメンテナンスがしにくくなる
固まる土の表面は掃除がしやすいのが利点ですが、砂利を敷くことでゴミや落ち葉がたまりやすくなり、掃除が難しくなります。また、砂利が動いて人が転びやすくなる・自転車が走りにくくなるといった問題も。
私が推奨する方法としては、「砂利敷きは見た目のアクセントとして、主動線や掃除が必要は固まる土」というゾーニングを行うことです。砂利を使う際は転倒リスクが少ないよう、粗目(5号砂利:13mm~20mm)の砂利を均一に敷くのが理想です。
固まる土に草が生えてきたときの対処法

「雑草が生えないはずなのに、ポツポツ草が出てきた」──これは、固まる土の使用者から非常によく聞かれる悩みです。ですが、これは固まる土自体に問題があるわけではないことが多いのです。
主な原因は以下の3つです:
- クラックから生えてきた
- 施工時に隙間ができた場所から草が生えている
- 施工厚が薄く、根が土に届いている
- 固まる土の上に土砂が流れてきて発芽している
つまり、「生えてきた草=施工不良や管理不足が原因」であることがほとんどです。対処法としては、除草剤(非浸透性タイプ)で処理するのが基本です。無理に引き抜くと固まる土ごと壊れてしまい、補修箇所がどんどん広がっていくため、除草剤を使って自然に枯らしていく方が安心です。
私の現場では、施工直後に定期的な掃き掃除をお願いすることが多いです。これだけで種の定着を防ぎ、ほとんど草が生えなくなるためです。
また、草の発生箇所が毎年同じ場合は、その部分の施工が甘かった可能性が高いため、部分補修を検討するとよいでしょう。
固まる土は犬走りに使える?デメリットはある?

「犬走りを固まる土にしたい」という相談も多く、実際に選ばれるケースは少なくありません。固まる土は表面がフラットで水はけも良く、雑草が生えにくいという点で、犬走りには向いている素材の一つです。
ただし、注意すべきは以下の点です:
- 硬化後の素材によっては滑りやすい・割れやすい
- 雨の多い地域では湿気がたまり、苔やカビが発生しやすい
- 建物側の基礎に水が溜まらないよう勾配調整が必要
実際のご相談でも、家の北側や日陰の犬走りに施工した場合、半年後に苔が発生したり、カビ臭が気になるというご相談があります。そのような場合は、天然系や透水性の高い製品を使用するか、部分的に砂利敷きに切り替えるなどの対策が有効です。
また、基礎まわりの通気性を確保したい場合は、そもそも使わない方がいいです。どうしても使いたい場合は、勾配をとって側溝に排水できるようにしましょう。
犬走りに固まる土を使う際は、メンテナンス性と建物への影響を考慮しながら、排水を第一優先として施工することが、長く安心して使うポイントです。
固まる土の事は分かったけど、自分ではどうする事も出来ない人へ
奈良県にお住いの方へ
あなたが奈良県にお住いの方であれば、次のような経験がないでしょうか?
「ネットで検索して色々情報を調べたけど、自分のお庭の場合、どの方法が適しているのか分らない…」
「調べすぎてどうすれば良いのか分からなくなって、考える事がだんだん面倒になってきた…」
そう思っていませんか?
そこで、造園・外構業者さんにお願いしようと考えてはいるけど、、、
「ネットの情報だけでその業者さんを信用していいのか不安だ…」
「ポータルサイトや一括見積りサイトや地元の業者さんのホームページを見たけど、業者さんの対応が悪かったら嫌だな…」
「結局、工事金額はいくらかかるの?」
そう思っていませんか?
これらが分からないと、いくらお庭の問題を解決したくても、不安感から二の足を踏んでしまっていて、ずっと困ったまま過ごさざるを得なくなってしまいますよね。
そこで、もしあなたが奈良県にお住いの方なら、私たち「西原造園の無料相談」がお役に立てるかもしれません。
毎月5名限定なので、今すぐ次のボタンをクリックして詳細を確認してみてください。
今月はあと1名
お問合せフォーム受付時間:24時間 年中無休